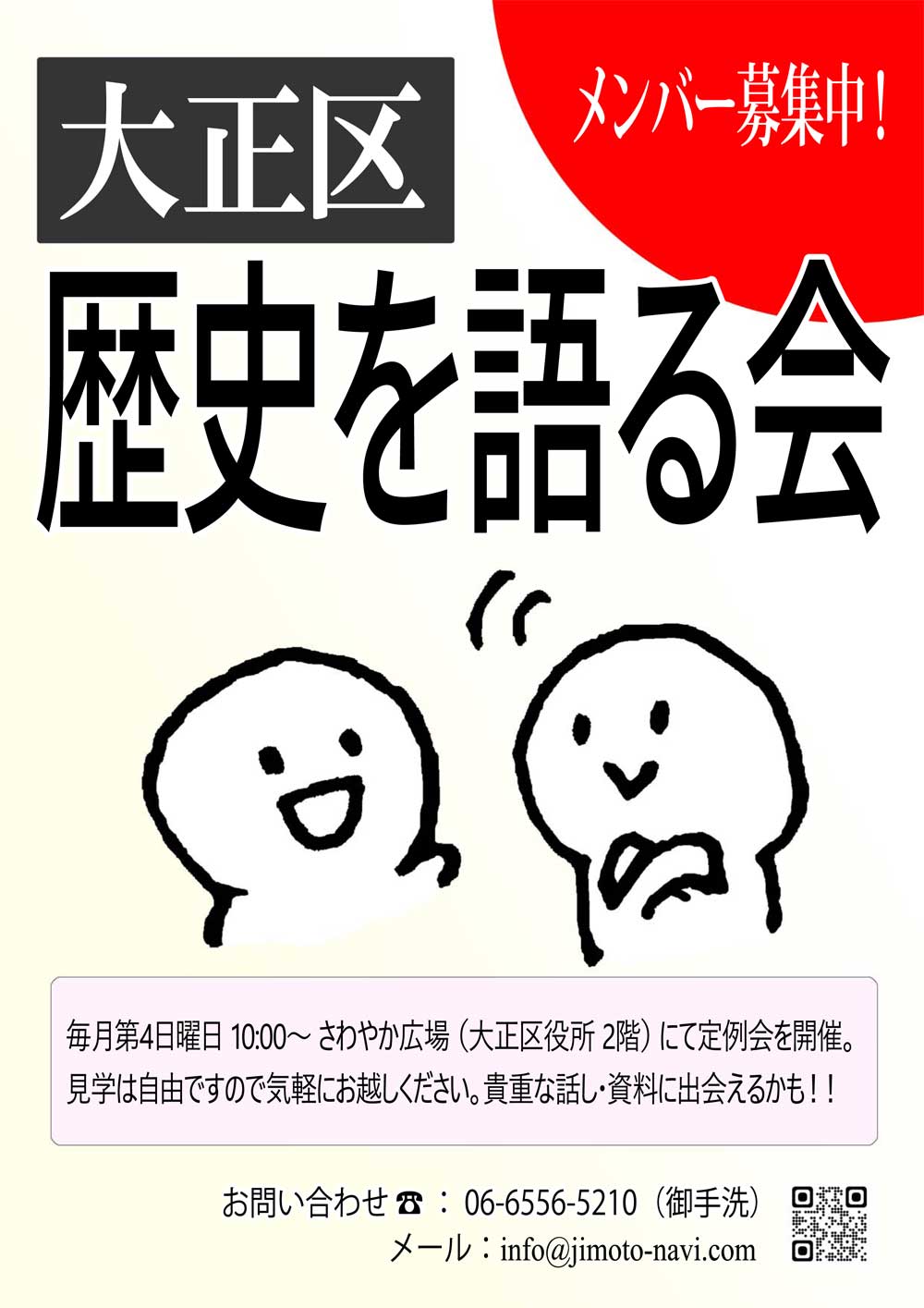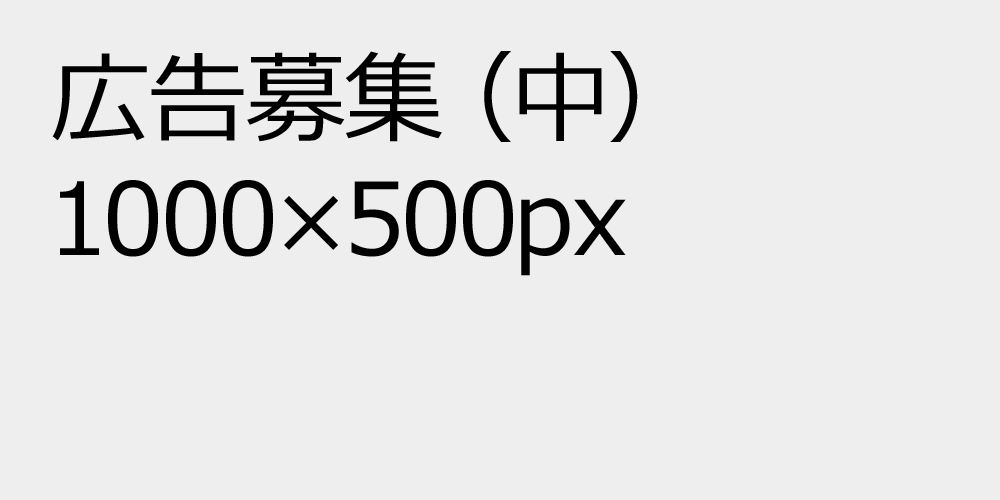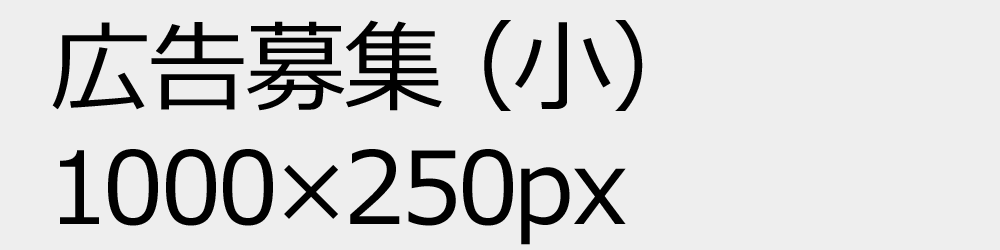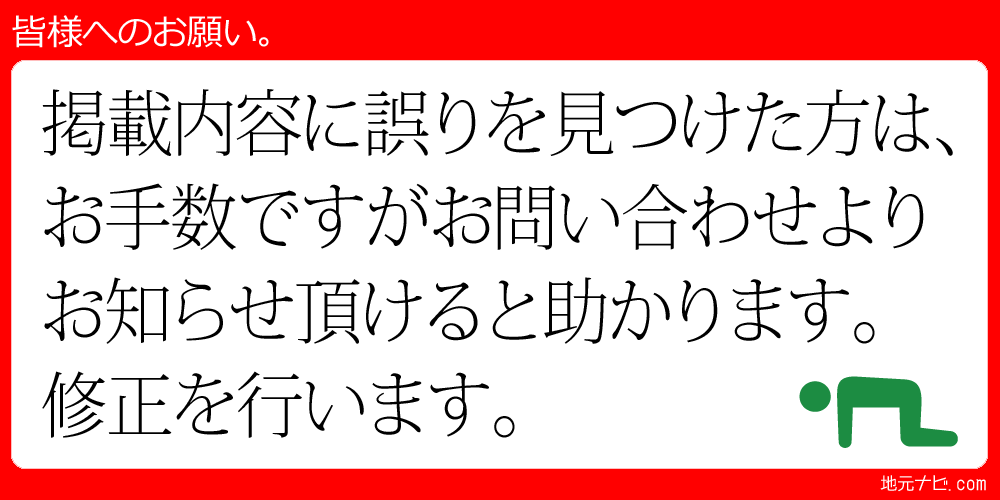大正区の歴史
大正区が施行されたのは1932年(昭和7年)。
今年で93周年です。
周りを海と川に囲まれた島のような形をしたこのまちが、脈々と現代に受け継がれるまでには様々なドラマがありました。
詳しい年表はこちら。
| 和暦(西暦) | 出来事 |
|---|---|
| 慶長15年(1610年) | 中村勘助(なかむらかんすけ)による新田の開発が始まる。 |
| 元禄12年(1699年) | 川村端賢(かわむらすいけん)により難波島(なんばじま)中央部の開削工事が行われ、木津川(きづがわ)の流路が一直線に。 |
| 明治8年(1771年) | 平尾新田が検知を受ける。昭和30年代までネギやスイカを栽培。 |
| 明治16年(1883年) | 三軒家(さんげんや)の大阪紡績会社(現・東洋紡)が日本で初めての蒸気式紡績機をイギリスから輪入。日本一の紡績工業都市へのきっかけに。 |
| 明治22年(1889年) | 町村制施行により、西成郡三軒家村・川南村(にしなりぐんさんげんやむら・かわなみむら)が発足。 |
| 明治30年(1897年) | 三軒家村および川南村の木津川右岸が大阪市へ編入され、西区に。 |
| 大正3年(1914年) | 第一次世界大戦勃発。南恩加島(みなみおかじま)にドイツ兵の俘虜収容所開所。(~1917年) |
| 大正4年(1915年) | 大正橋竣工。やがて大阪市電九条高津線が開通。 |
| 大正6年(1917年) | 西区の西道頓堀・西長掘等から集団移転してきた木材業者による西日本有数の木材市場が誕生。 |
| 大正9年(1920年) | この頃沖縄からの出稼ぎ就労者が増加。 |
| 大正14年(1925年) | 新設の港区に含まれる。 |
| 昭和2年(1927年) | 鶴町にゼネラルモーターズ(GM)の自動車工場が開業。(~1941年) |
| 昭和4年(1929年) | 木津川飛行場共用開始。(~1939年) |
| 昭和7年(1932年) | 港区より分区され大正区が発足。 |
| 昭和15年(1940年) | 防潮堤が完成。(尻無川・木津川) |
| 昭和36年(1961年) | 国鉄大阪環状線全通。大正駅開業。 |
| 昭和45年(1970年) | 千島公園に昭和山(標高33m)誕生。 |
| 昭和47年(1972年) | 米信託統治下にあった沖縄が日本に返還、沖縄県に。 |
| 昭和50年(1975年) | 第一回大正区民まつり開催。 |
| 平成元年(1989年) | アメリカ映画「ブラック・レイン」で東船町の中山製鋼所がロケ地に。 |
| 平成6年(1994年) | 新木津川大橋開通。 |
| 平成7年(1995年) | なみはや大橋開通。 |
| 平成9年(1997年) | 大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線開通。大正駅開業。 |
| 平成15年(2003年) | 千歳橋完成。 |
| 平成24年(2012年) | 沖縄本土復帰40周年・大正区制80周年記念事業として、千島公園にて「綱(ちな)・ちゅら・エイサー祭~与那原大綱曳(よなばるおおつなひき)in大正区~」開催。 |
| 平成25年(2013年) | 連続テレビ小説「純と愛」で大正区が舞台地に。 |
「大阪市くらしの便利帳 大正区」平成27年10月発行より
地名に残る、大正の歴史
| 地名 | 歴史 |
|---|---|
| 三軒家(旧三軒家村) | 木津川尻の小島であったこの地を、木津村の中村勘助(なかむらかんすけ)が開発しました。 その当時に、三軒の民家が建てられたからだといわれています。 |
| 千島(千島新田) | 千島新田は、東成郡千林村(せんばやしむら)(現旭区)の岡島嘉平次(おかじまかへいじ)により、宝歴7年(1757年)から順次開発。 地名は千林村の「千」と、姓の岡島の「島」をつなぎ合わせて「千島新田」と命名されたことに由来しています。 |
| 南恩加島(南恩加島新田) | 南恩加島新田は、2代・3代岡島嘉平次によって開墾、恩加島新田と称しました。 この名称は名前の岡島を恩加島と換用したものですが、開墾者の恩を忘れぬようにしたいという意味もあったようです。 |
| 泉尾(泉尾新田) | 和泉国大鳥郡踞尾村(いずみのくにおおとりぐんつくのおむら)の北村六右衛門(きたむらろくえもん)が開墾。 開発者の北村六右衛門の国名「和泉」と村名「踞尾」から一文字づつを採り命名したといわれています。 |
| 小林(小林新田・岡田新田) | 東成郡千林村の岡島嘉平治が開墾した小林新田から命名され、小林は千林村から一文字採った呼称であることに由来してます。 |
| 北恩加島(北恩加島新田) | 恩加島新田を2分したときに、南恩加島と北恩加島に分けられました。 |
| 北村(泉尾新田) | 泉尾新田の開発者である北村六右衛門の苗字から命名したものといわれています。 |
| 平尾(平尾新田) | 大阪江戸掘の平尾与左衛門(ひらおよざえもん)が開拓。 与左衛門の姓をとって「平尾新田」と命名されたといわれています。 |
| 鶴町・船町・福町 | 「鶴町」は万葉集巻六の田辺福麻呂(たなべのさきまろ)がよんだ「潮干れば葦辺(あしべ)に騒ぐ白鶴の妻よぶ声は宮もとどろに」の鶴と、 「船町」は同じく「あり通う難波の宮は海近(うみちか)み海女娘子(あまをとめ)らが乗れる船見ゆ」の船と、 「福町」は詠者の名前からとったものです。 |
「大阪市くらしの便利帳 大正区」平成27年10月発行より